
猛暑の天神に、ひんやりと涼をもたらした妖怪提灯の数々。8月1日~12日、6階スカイロビースクエアで開催された「出張 奇怪夜行 in ONE FUKUOKA BLDG.」では、妖怪が描かれた特別な八女提灯が飾られ、その涼やかで幽玄な空間が多くの人を魅了しました。これらを手がけたのは、八女市で210年続く提灯屋「伊藤権次郎商店」の8代目・伊藤博紀さん。伝統を守りながら革新的な挑戦を続ける伊藤さんに、家業への想いと新たな試みについて伺いました。
伊藤: 15歳から提灯づくりを始め、高校時代にはひと通りの技術を身につけていたので、そのまま継ぐこともできましたが、いや待てよ、と。伝統工芸の世界は「作る」ことに全力を注ぐあまり、マーケティングやブランディング、プロモーションが見落とされがち。地方特有の情報の遅さや高齢化の課題もあって仕方のないことですが、まずは継ぎ手として、外の世界で経験を積んで、一流企業の情報のスピード感や組織の仕組みを学ぶことが必要だと考えました。
伊藤: ファッションビルでのプロモーション事業です。飲食やアパレル、アニメ、芸能など幅広い業界と関わり、世間で注目を集めるコンテンツを取り入れながら企画を立て、集客や販促につなげるのですが、イベントの企画は足し算・掛け算で生まれていることを気付かされました。「人はどんな瞬間に心を動かされるか」を考え続け、ものごとをエンターテインメントとして魅せていく“企画力”は本当に鍛えられましたね。
またビルの空間演出やディスプレイも担当して、"魅せ方"の重要性も体感。それが今の提灯の展示や演出にそのまま活きています。
伊藤: 伝統工芸の世界は保守的と思われがちですが、うちの職人たちはとても柔軟。僕が家業に戻り、最初に取り組んだ倉敷デニムを使った『デニム提灯』も「面白そう!」と賛同してくれました。デニム提灯は八女提灯の可能性を広げるためのチャレンジ企画で、提灯=和紙という固定観念を壊し、日本の伝統と対極にあるアメリカ文化の象徴・デニムを組み合わせることで新しいストーリーを生み出したかったんです。
また、企画や制作と同じくらい僕が大事にしているのは、分業制で作られる提灯を“完成形"として職人全員に見せること。地方の職人たちは自分の手がけたものがその後どう使われているかを知る機会が少ないので、「あなたが作ったパーツが博多座の正面玄関にこうやって飾られているよ!」と写真で共有し、現場の様子やSNSでの反応もしっかり伝えます。すると社内のモチベーションが上がり、自然と「次は何をするの?」とみんなの創作意欲も高まります。
伊藤: 実はSNSがきっかけなんです。当時、無地の背景に商品を置く撮影スタイルがInstagramの主流でしたが、僕は「提灯は使われてこそ生きる」と思い、実際に現場でどう灯っているか、人の営みや空間に八女提灯がどう存在しているかを撮って発信していました。例えば、博多の山笠で男衆が提灯を手に持って走る姿。あの光景こそが提灯の魅力を表していると思いませんか?
実際にSNSを通して依頼が来たのは2016年の頃。「映画のセットで使いたい」という内容だけで詳細は伏せられていましたが、会社員時代の営業脳で「こんな提灯も作れます」「この見せ方はどうですか」と積極的に提案。後からそれがディズニー映画『くるみ割り人形と秘密の王国』だと明かされたときはビックリしましたね(笑)。
その3年後、次はNetflixオリジナル映画『レベッカ』の舞台美術の提灯も手掛けることに。当時僕がこだわったのは、日本人ならではの美意識です。掛け軸の水墨画でも見られるような“間”や“引き算”の美学は、日本人特有の表現。提灯も絵柄を最小限に留め、余白を残しながら儚げな美しさを引き立てました。
伊藤: CRAFCULTには、「工芸を崇拝する」という意味があります。江戸時代から続く老舗の伊藤権次郎商店は、いわば“守りの強い盾”。ただ、尖った挑戦をすると「伝統を守って」と言われる側面もあって…。そこで株式会社CRAFCULTというベンチャーを立ち上げ、“守り”の伊藤権次郎商店と、“攻め”のCRAFCULT、両方を使い分けられるようにしました。
博多祇園山笠や唐津くんち、博多座、神社に奉納する提灯づくりは伊藤権次郎商店として務め、今回の「奇怪夜行」のような企画性のある展示や空間演出はCRAFCULTが行う。僕自身、提灯職人であり、クリエイターでもあるから、肩書きを使い分けながら自由に表現するためにもCRAFCULTは必要でした。“POP工芸”という新しいジャンルを掲げ、伝統と新しさを掛け合わせた活動をしています。
伊藤: ファッションビルの仕事を退職後、伝統工芸品としての提灯だけでなく、何かオリジナルで自由に表現したいと思ったのがきっかけ。昔から好きだった妖怪を提灯に描いてみたら、すごく面白くてのめり込みました。
最初は10~15灯を作り、工房内での展示からスタート。チラシのデザインや配布、PR活動も全部ひとりで行う手作りイベントでした。2~3年続けた頃にメディアにも取り上げられ、県庁の職員の方から柳川市の「柳川藩主立花邸 御花」を紹介していただいたんです。それ以降、御花さんでの展示が毎夏の恒例イベントに。毎回テーマを変えていて、今年は「キキキの奇怪夜行」と題し、僕の妖怪提灯と、水木しげる先生のチーフアシスタントを務めた佐々岡健次先生が描く妖怪画を特別展示しました。
伊藤: 本音を言うと、商業施設は避けたい場所(笑)。御花さんのように歴史的建物なら提灯1灯でも強いインパクトを与えられますが、商業施設という情報量の多い空間では埋もれてしまうし、空間全体が明るいので提灯本来の魅力である光の陰影も表せなくて。でも、多種多様な人が行き交い、多くの人の目に留まるワンビルでの展示は、挑戦する価値があると感じました。
このスカイロビーに映えるように、色や造形を強調し、光に頼らない見せ方に挑戦しました。30灯の妖怪提灯を一堂に並べ、集合体の迫力と怪しさ・美しさの塩梅をうまく設計しましたね。
ちなみに、ONE FUKUOKA HOTELでの空間演出はミニサイズの提灯を使い、シンプルに墨の線画だけで表現。空間に合わせてデザインや見せ方を調整できるのは、ブランディングから企画、制作、プロモーションまで一貫して自分が手がけるからできること。芯をブラさず、思いをそのまま表現できるのが僕の強みです。
伊藤: うちは九州で一番古い提灯屋とあって、「九州の提灯は僕が最後の防衛線」だと感じています。老舗が一番ぶっ飛んだことをやらないと、誰も新しいことに挑戦できなくなるでしょう。だから厚く大きな壁を僕が壊している最中です。
今はブランドのネームバリューより、「誰がどういう思いで作ったか」というサイドストーリーに共感してモノが選ばれる時代。工芸も同じで、「八女提灯」という名前だけじゃ消費者に響かない。でも、CRAFCULTとして表現すれば若い世代にも注目してもらえる。まずは“個”である自分が前に出て発信し、「この作品って八女提灯なんだ」と歴史や文化の背景を知ってもらう流れを作ることが重要だと思います。
伊藤: 伊藤権次郎商店では櫛田神社、水天宮、熊本の八千代座、博多座など名だたる場所に提灯を奉納させていただき、最近では福岡空港国際線ターミナルの提灯飾りも担当しました。これからも誠心誠意を込めて日本の伝統、八女提灯を守り続けていきたいです。
CRAFCULTの活動としては、もっと国内外でクリエイティブな活動を広げていきたいですね。ただ、「提灯の形」を変えるつもりはありません。江戸時代から連綿と続くこのシルエットこそ、日本人の美意識に刻まれている黄金比ですから。形はそのままに、描くものや素材をどう創造していくか―― すべて自分の手で作れるからこそ、表現の可能性を探り、守るべきものは守りながら、新しいことに果敢に挑戦し続けていきたいと思っています。

ワンビルでの展示イベント最終日、特別企画として提灯の絵付け体験が開催されました。参加者は絵付け職人の指導のもと、高さ約20cmのミニ提灯に思い思いの絵柄を描き、個性豊かなオリジナルの提灯が完成。
「天神で伊藤さんの出張イベントが行われていると聞いて駆けつけました。絵付け教室は貴重な機会だからうれしい!」と、毎年「奇怪夜行」を観に柳川まで通うファンが参加。また、「実際に筆を持ってみると想像以上に難しくて、改めて職人さんの技術の高さを実感しました」という参加者の声も。体験や好奇心を通じて伝統工芸の奥深さを知り、その価値を肌で感じてもらう――伊藤さんが目指す「伝統工芸のエンタメ化」。人々の心を動かす瞬間が、まさにこの空間に広がっていたように感じます。
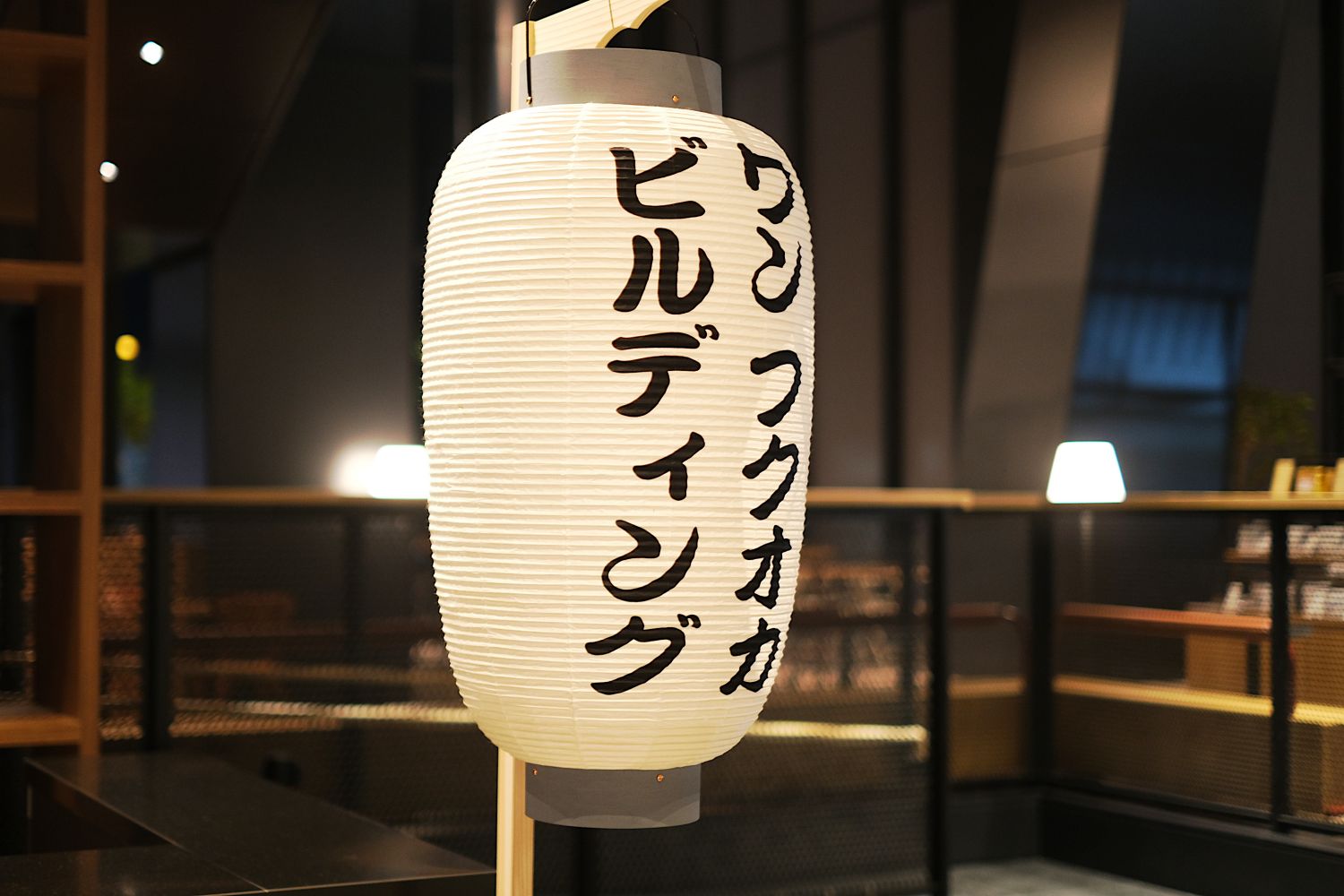
Instagram https://www.instagram.com/crafcult/
HP https://chouchinya.jp/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Interview & Text & Photo_ Maiko Shimokawa
Edit_ Taku Kobayashi
伊藤 博紀(いとう ひろき)
福岡県八女市出身。「伊藤権次郎商店」8 代目代表、「株式会社クラフカルト」代表取締役。
伝統工芸品である八女提灯の作り手として家業を守りながら、八女提灯を工芸品としてだけでなく、空間演出・POP 工芸(現代アート)など、新たなフィールドへと昇華している。世界的に有名な映画の美術セットや海外商業施設、イベント演出や装飾、インテリア等に昇華するなど、新たな提灯の可能性を広げる活動に尽力。数百の神社への提灯奉納、博多座の大提灯、福岡空港国際線ターミナルの提灯装飾、ディズニー映画の装飾、パリのパレ・ロワイヤル(元王宮)での展示など実績多数。