MEETS DIFFERENT IDEAS, LIFE×ART×CULTURE×BUSINESS×IMAGINATION×CO-CREATION.
MEETS DIFFERENT IDEAS, LIFE×ART×CULTURE×BUSINESS×IMAGINATION×CO-CREATION.





ONE FUKUOKA PROJECT.
福岡で生まれ育ち、上京して、数々のヒット曲を生み出してきたシンガー・ソングライターの財津和夫さん。天神のまちで青春時代を過ごし、かつては西通りで若者の人気を集めたカフェ「Hebe(ヘーベ)」を手がけたことも。2019年から「西鉄グランドホテル」で続けている作詞講座「言葉が歌になる時」も好評で、天神に縁が深く、現在は福岡で過ごす時間を少しずつ増やしているという財津さんに、当時の思い出や作詞講座を続ける理由、変わりゆく天神への想いを伺いました。

シンガー・ソングライター、作曲家、音楽プロデューサー
1948年、福岡県生まれ。1972年に「TULIP(チューリップ)」としてメジャーデビューし、1978年からはソロ活動もスタート。作曲家として楽曲提供やアーティスト・プロデュース、ミュージカル音楽制作を手がけ、近年は大学教授、作詞講座の講師やラジオパーソナリティも務めるなど、多彩な才能を発揮。2022年4月から始まったTULIP 50周年ツアーは大好評を博し、アンコール公演含めた全64本が2024年7月に終了した。2024年秋からは姫野達也氏をゲストに迎えたソロコンサートも始動。

僕は東区の生まれで、小学校から高校まで生活圏はずっと東側でした。遊びに出るようになったのは高校生くらいからで、思い出の一つも高校生の頃。天神の真ん中にあった「福岡スポーツセンター」の前に、センターシネマっていう映画館があったんです。その頃はまだ床が昔の土間みたいな造りで、土の上に椅子が並んでいるような感じでした。そこで、ビートルズの映画「ビートルズがやって来る ヤァ!ヤァ!ヤァ!」が上映されて、友達と観に行ったんです。
これは、僕の人生を変えましたね。あまりにもかっこよすぎて、もう衝動的に“バンドをやりたい!”って思ったんです。ビートルズを見てエレキギターにも憧れて……だけど、当時はエレキギターを持ってるだけで不良、アウトサイダー扱いされたんですよ(笑)。それに高くて買えないから、僕は持っていたクラシックギターでビートルズを真似て、全然感じは違うけれど、一生懸命コピーしていました。









天神が身近になったのは、西南学院大学に入学してからですね。当時の天神は福岡唯一の街というイメージで、福ビルにはおしゃれなインテリアショップ「NIC」なんかもあった。学校帰りは必ず天神へ寄って、バンドを組んでからは「照和」にも出るようになり、この頃は自分の庭のような感覚でした(笑)。当初の「照和」はロシア民謡や昭和歌謡が歌われる歌声喫茶で、学生運動が盛んな時代だったので反戦を歌うフォークソングも主流だった。次第にビートルズの影響でバンドを始める連中も増え、僕らが出られるようになっていったんです。そこから若者の、バンドの巣窟になりました。あの頃は歌えるならどこでも!という感じで、ビル屋上のビアガーデンでみかん箱に乗って歌ったりもしていましたね。誰も聞いていなくても、歌えるだけで楽しかった。上京してデビューしてからはそう簡単に帰って来れなくなりましたが、当時まだお店が少なかった頃の西通りには、「Hebe(ヘーベ)」(※)を開きましたね。福岡にも東京みたいなかっこいいカフェがあったらいいのに……というところから話が進み、絵も好きだったので色々と飾って、あの店が生まれました。
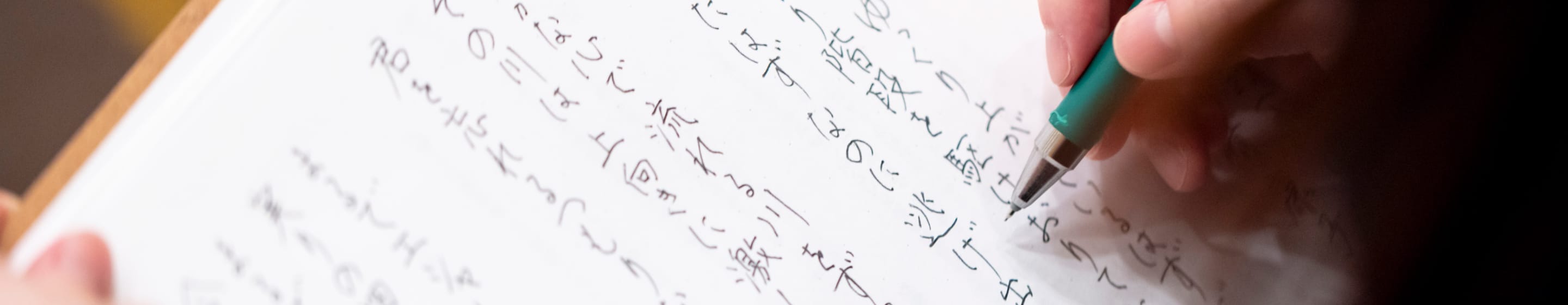
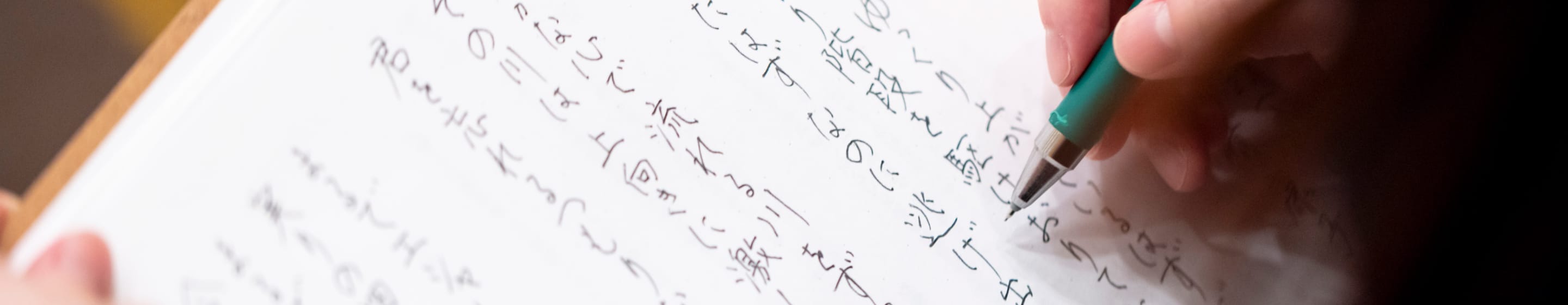

変わりゆく天神の街について思うことですが――。物事には、いつも良いところと悪いところがありますよね。良いところはどんどん街が大きくなって、東京と同じような感覚で生きていけること。変化した先の未来を見たいという楽しみもあります。一方で、僕らみたいにこの場所をふるさとだと思っている、昔の良さを知っている人間が、変わっていくことに不安や寂しさを感じていることも確か。福岡を一度出た者にとって、僕にとっては“福岡の風”って特別で。福岡の風に当たりたい、触れたいっていう、何とも言えない思いがあるんですよね。福岡に降りたら、風が東京とは全然違う。那珂川に架かる中洲の橋の上に立つと、川を通って海に流れる風や海から吹いてきた風がすごく気持ちいいんです。どうしようもない袋小路ばっかりになるんじゃなく、きちっと都市計画をしてもらって、“めっちゃいい街だね”って、世界に誇れるような場所になって欲しい。これからも風の気持ちいい、人が生きていくのに気持ちのいい街であって欲しいと思います。
取材に伺ったのは作詞講座シーズン11の開催日で、会場は満席。全国から訪れる受講者の方々の熱量は高く、いつも時間をオーバーしてしまうほどなのだとか。財津さんは「受講者の方々とは歳が近いこともあって、話が合うんですよ。近所の人と縁側でよもやま話をするような“陽だまり感覚”を楽しみながら、大切にしたい、続けられるだけ続けていこうという気持ちでいます」と一言。その柔らかな声と表情には、この時間への、福岡への愛情と居心地の良さが詰まっているようでした。