MEETS DIFFERENT IDEAS, LIFE×ART×CULTURE×BUSINESS×IMAGINATION×CO-CREATION.
MEETS DIFFERENT IDEAS, LIFE×ART×CULTURE×BUSINESS×IMAGINATION×CO-CREATION.





ONE FUKUOKA PROJECT.
初代福岡藩主・黒田長政が、福岡城を築城する際に現在の場所に遷座され、416年の歴史を持つ警固神社。その宮司を務める前田安文さんは、氏子区域の居住者減少や高齢化などから将来の神社護持に一抹の不安を抱き、地域の人々の拠り所となるお祭り「月華祭」の開催や、コミュニティハブとして地域に開かれた未来の神社像を求めて、警固神社のリブランディングを遂行中。そんな前田さんが、未来の天神のまちに願うこととは。

警固神社 宮司
1960年福岡市生まれ。大名小学校、舞鶴中学校に通い、新天町や因幡町商店街(現・天神1丁目付近)で遊んだ生粋の天神っ子。國學院大学・文学部神道学科を卒業後、警固神社の権禰宜、禰宜を経て、2010年警固神社を含む7社の宮司に就任。400年以上の歴史を持つ神社を後世に伝えるため「変わらないために変える」ことを決意。2016年よりリブランディングをスタートし、2022年には飲食店やオフィスが入居する社務所ビルをオープン。
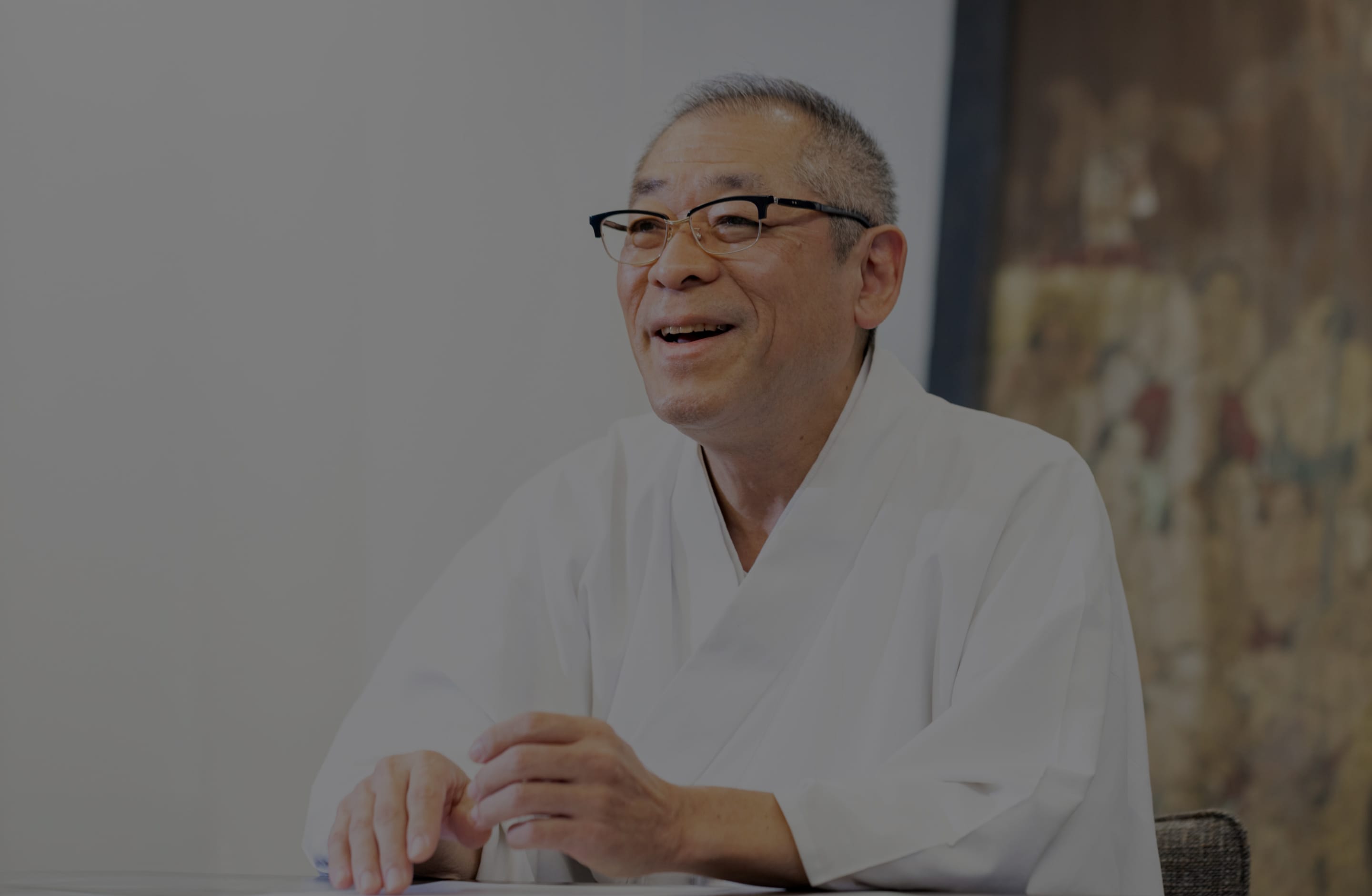
私が大名小学校に通っていた1960年代は、天神には今よりもたくさん人が住んでいました。放課後ランドセルを置いて遊びに行ったのは、新天町や因幡町商店街。小学3年生の時に西鉄グランドホテルが建ち、昼休みに工事現場の方が、ビルの上から紙飛行機を飛ばしてくれたのを覚えています。中学3年生の時に、西日本新聞会館が完成。神社から見えていた中洲の風景が見えなくなりました。スポーツセンターでアイススケートをして、映画を見た後にナイルのカレーを食べに行くのが、一番贅沢なパターンの休日の過ごし方。
岩田屋へ行く時だけは、長袖シャツに半ズボンと革靴で。その時代、百貨店は憧れの存在でした。そんな私が天神を離れたのは、神職の資格を取るために進んだ大学の4年間だけ。その間にも天神地下街ができて市内電車がなくなり、地下鉄が開通するなど、目まぐるしい勢いで発展し、都市化が進むにつれて、多くの同級生が引っ越していったのが寂しかったですね。









警固神社の宮司に就任したのは2010年のこと。その頃には氏子区域の居住者も減り、2014年には3つの小学校が一つに統合されました。そのような中で、地域のコミュニティハブの役目を警固神社が担えればとの思いで始めたのが「福岡まつり月華祭」です。居住者の減少や繋がりの希薄さは、神社の運営にも関わってきます。私は警固神社以外にも6社お守りしている神社があるのですが、その営繕費やご遷宮の費用を蓄える施策として、2022年、境内に飲食店やオフィスが入居する複合的な社務所ビルを建てました。また400年以上使っていた黒田家ゆかりの“下り藤”の社紋を、警固神社を象徴する「警め(いましめ)固 る(まもる)」から一字いただき、新しい社紋にして、お守りも刷新しました。このリブンディングには様々なご意見をいただきましたが、7社すべてを100年後、200年後に残すのが私の仕事。警固神社が伝えてきた変えてはいけないものを守るために、変わることも大切だと考えています。









警固神社として大事にしていきたいのは、信者の方々をはじめ、地域とのつながりです。天神を訪れたついでに立ち寄ってくださるような方にも、気持ちよくお参りをして、背筋が伸びるような“いい気”を感じていただくために、しなやかかつとんがった神社でありたいと思います。そのためには、お掃除はもちろん、日々のお務めやお祭りを実直に行なっていくことが大切です。土地柄、お勤めの方から観光の方まで、多様なアイデンティティを持った方が集まる神社なので、地域に開かれた交流拠点を目指すとともに、歴史や文化をお伝えする場所でありたい。物事の結果は、コツコツと何年も続けて初めて、実を結ぶものだと思います。私たちが種を撒き、次の世代が水をやって花を咲かせ、そのまた次の世代が種まきし育てていく。大切なのは未来をイメージして行動すること。まちづくりも同じだと思うので、私が生きているうちは、生まれ育った街に貢献できるように、チャレンジしていきたいですね。
前田宮司によると、神社の境内に複合ビルを建てたのは、警固神社が日本初なのだそう。前例のない挑戦へと宮司を突き動かしたのは、100年後、200年後の神社を守る、人々への思いです。取材に訪れた日、社務所ビルの1階にオープンした九州初の「ブルーボトルコーヒー福岡天神カフェ」から出てきたカップルが、神社にお参りして帰る姿が見られました。警固神社が歩みだした新たな時代の始まり。その一端を垣間見た気がしました。